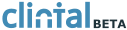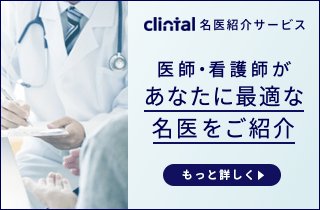「かかりつけ医」「一般病院」「高度医療機関」のそれぞれの役割と違い

医療機関の分類
ここまで、「かかりつけ医」、「一般病院」、「高度医療機関」と医療機関分類ごとにそれぞれの果たすべき役割などをご紹介してきました。
ただ実は、これらの分類は正確に定義されたものではありません。例えば、制度上では「20床未満の医療機関を診療所」「20床以上の医療機関を病院」と定義したり、特定の要件を満たした病院を「特定機能病院」「地域医療支援病院」「がん診療連携拠点病院」として認定し、診療報酬上の優遇措置を行ったりしています。
またそれとは別に、医療機関は経営母体で分類されたりもします。「国立」「地方自治体」「社会保険団体」「赤十字」「民間」などです。
しかし、これらの分類はどちらかというと医療者側(特に経営陣)のための分類であって、患者さんが実際に受診される際に、あそこは地域医療支援病院なんだ、などと気にしたことはほとんどないと思います。患者さんからすると、だからどう、ということもなく、受診しても特に違いはなく、どこも特に変わりない大きな病院にしかみえないからです。
しかし、最初の3分類に関しては、やや定義が曖昧な部分はありますが、しっかりと役割をご理解いただき使い分けていただく必要があると思っています。また今後も触れていきますが、それが自分自身のため、そして他の人のためになるからです。(参考:「受診する」って難しい!:① “初診料”)
医療機関の違いをおさえておきましょう
適切な医療機関を選ぶために、きちんと医療機関の違いをまとめておさえておきましょう。
それぞれの特徴は、医療機関① 「かかりつけ医」の役割、医療機関② 「一般病院」の役割、医療機関③ 「高度医療機関」の役割、で説明済みですが、それぞれの医療機関の特徴や役割を以下にまとめました。
一概に医療機関といえど、この様にそれぞれ違う役割を担っています。私も正直申し上げて、大学生の頃、お腹が痛くなり39℃まで熱があがってきたために、大学病院のすぐそばに住んでいたので、大学病院を受診してしまったことがあります。。(しかもたまたま消化器内科教授の初診外来にまわされました。。)今振り返ると自分にも他の患者さんにもよくないことをしたなと思います。
医療機関を選ぶのはあなたです
こうした知識はあなたの健康を守るだけでなく、お金や時間などのムダを省くことができます。さらには軽症な時には、受診すべきではない高度医療機関を受診しないことで、本当に必要な人が適切な医療を受けることができます。
現在の日本の医療はフリーアクセス、つまり患者さん自身が「自由なタイミング」で「自由に受診する医療機関」を選ぶことができます。あなたには自由に受診する権利が与えられているのです。
 しかし例えばイギリスでは、かかりつけ医(=家庭医(General Practitioner))は登録してあるところを受診しなければならず、かかりつけ医からの紹介状がなければ、専門医や大きな病院を受診することができません。つまり、いろいろなかかりつけ医を自由に受診することもできなければ、より大きな病院をいきなり受診するということもできないです。アメリカでは、受診できる医師を保険会社に制限されていたりします。
しかし例えばイギリスでは、かかりつけ医(=家庭医(General Practitioner))は登録してあるところを受診しなければならず、かかりつけ医からの紹介状がなければ、専門医や大きな病院を受診することができません。つまり、いろいろなかかりつけ医を自由に受診することもできなければ、より大きな病院をいきなり受診するということもできないです。アメリカでは、受診できる医師を保険会社に制限されていたりします。
患者さんの良識ある行動を信じ、どこでも自由に受診ができるシステムを作り上げた日本は非常に素晴らしいと思います。自由であるがゆえに受診先の選択には責任も伴います。皆が適切な医療を受けられるよう、適切な選択を心がけましょう。
「どの名医に治療をお願いすればよいのかわからない!」とお悩みの方には、クリンタルの名医紹介サービスをお勧めしています。クリンタルが独自に厳選した「3,500人の有数の専門医」「35,000人の街の名医」の中から、あなたの病気/症状やご希望を考慮して、クリンタルの医師が最適な名医をご紹介します。