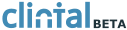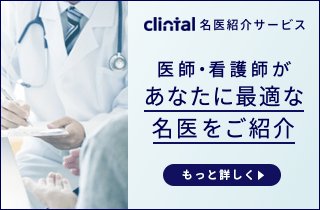首が痛い!痛みで首が回らないって一体、何が起きた?

首が痛いのが続いている
首が痛いという人に症状を尋ねると「朝、起きたときから痛い」という人もいれば「疲れると痛くなる」という人、また、「急に痛くなる」「徐々に痛くなった」など症状の現れ方はさまざまなようです。首の痛みを引き起こすのは首の骨(頸椎、けいつい)の変形や首にできた腫瘍などの病気の影響、さらに、姿勢が悪い、枕が合っていないなどの原因が考えられます。
「首が痛い」と感じながら生活するのはツラいことですが、痛いだけでなく手足が動きにくくなったり、排尿に問題が生じたり、首の痛みによって日常生活に支障がでることも少なくありません。気になる症状が続いているときは受診して、適切な対処法で首の痛みを軽くしましょう。
そもそも首が痛いのはなぜか
首が痛くなる理由をお話しする前に、首の痛みに関係する骨の構造や良い姿勢について確認しておきましょう。
首や背骨はS字の形をしている
健康な人の骨は、体を横から見たときに首の辺りは少し前方に、背骨は後方に湾曲して緩やかなS字状のカーブを描いています。しかし、姿勢が悪い人、老化やケガなどで骨の形が変わった、あるいは本来の位置からズレてしまうとS字カーブにならず、重い頭をのせている首に負担がかかりやすいのです。
首の痛みには姿勢の影響が大きい!
頭を前後左右に傾けたり、左右にねじったり、首をグルッとひと回りさせるなどさまざまな動きができるのは、首の関節や周辺にある筋肉がうまく働いているおかげです。背筋を伸ばして骨盤の上に首や背中がバランスよくのっていると重い頭を支えるのに効率がよく、首の負担も少ないといわれています。しかし、背中を丸めたり、首を傾けたり、バランスの悪い姿勢を続けていると首の筋肉が緊張したままとなり、血流も悪くなって首のコリや痛みを起こしやすいのです。
特に、スマホやパソコンに熱中していると、気づいたら数時間たっていたという経験は珍しくないでしょう。「首が痛い」というときには日常の中で身についてしまった悪い姿勢が原因になることも多いです。
首が痛いのは老化で椎間板に変化が起きた?
首の骨、頸椎は全部で7つの骨からできていますが、骨と骨の間にはゼリー状の椎間板(ついかんばん)という物質があり、衝撃を吸収するなどクッションのような働きをしています。この椎間板の働きによって首や背中、腰などの骨が安定し、関節も滑らかに動かせるのです。
しかし、椎間板は加齢や姿勢の悪さ、ケガなどによって飛び出したり(ヘルニア)、水分が少なくなって小さくしぼんだりして弾力が失われることもあります。すると、骨と骨の間にすき間ができてしまうので、そのすき間を塞ぐために新たに骨が作られるそうです。新しくできた骨はトゲのような突起(骨棘、こつきょく)となって神経を圧迫するので痛みが現れます。また、椎間板の変化によって骨同士がぶつかったり、擦れ合ったりして頸椎も変形して神経を圧迫することも少なくありません。
「首が痛い」というときは脊髄(せきずい)という首や背骨の中を通る神経を骨棘が圧迫している可能性があり、その場合には手のしびれや指を拡げにくいなど他の症状を伴うことが多いです。
骨の位置がズレることも原因になる
首の骨や椎間板の位置が本来のところからズレてしまうことも神経を圧迫する要因の一つです。たとえば、強い衝撃を受けて頸椎に亜脱臼(あだっきゅう)という位置のズレが起こると首が痛くなることもあります。首の亜脱臼は脱臼のように関節が外れてしまう訳ではありませんが、自然に回復する軽いレベルから、ときに致死的な事態を招く重いレベルまであり、重症度の差が大きいです。
首が痛い原因としてはどういう病気が考えられるか
首の痛みは首の病気やケガのほかに、首の腫瘍や感染症などが原因となっている可能性があります。
頸椎や関節などの障害で首が痛い場合
・頸椎症(頸部脊椎症)で首が痛い場合
加齢などによって頸椎が変形し脊髄などの神経を圧迫すると、首が痛い、手や指、脚がしびれるなどの症状が起こります。頸椎症になると肩や背中など広い範囲が痛いということも多く、さらに、排尿や排便がしにくいといった排尿障害になる人もいます。
・頸椎椎間板ヘルニアで首が痛い場合
頸椎椎間板ヘルニアは頸椎と頸椎の間にある椎間板が飛び出してしまった状態で、飛び出した椎間板が神経を圧迫すると頚椎症のように首の痛みや手足のしびれなどが現れます。痛みは次第に強くなる傾向があるので放置しないことが重要です。
・頸椎捻挫(むち打ち症)で首が痛い場合
スポーツや交通事故などで衝撃を受けると、頸椎捻挫になって首が痛くなることもあります。頸椎捻挫は首の筋肉や靱帯が強く引き伸ばされたこと(過伸展)によって筋肉や靱帯に損傷が起きている状態です。首が痛いだけでなく、手足のしびれやだるさ、筋力の低下なども認められます。
・顎(がく)関節症で首が痛い場合
首の痛みの原因としては、顎(あご)の骨や筋肉に障害が起こった顎関節症も考えられます。顎関節症は顎の周りにある筋肉が緊張した状態のため首コリや肩コリが起こりやすく、痛みとして感じることも多いです。
がんや感染症などが原因となって首が痛い場合
首に発生したがんなどの腫瘍が、周囲の神経を圧迫するくらい大きくなると首に痛みが現れるようになります。また、首が痛いときに発熱もあるとすれば、肺炎などの感染症にかかっている可能性もあります。
さらに、強いストレスが原因となって首を回せない、首が痛いということもあるようです。ストレスによる自律神経の乱れが原因となり、首を動かすときに使う筋肉が過度に緊張しているためと考えられます。この場合、首の痛みはある日、突然、起こることが多いです。
どれぐらい首が痛いと病院の受診が必要になるのか
首の痛みが徐々に増強している場合
首の腫瘍による痛みの場合、腫瘍が大きくなるにつれて痛みが強くなる傾向があります。腫瘍には良性のものもあり、がんのように悪性とは限りません。しかし、安静にしていても首の痛みが続くときは整形外科で原因を調べてもらいましょう。
首が痛いだけでなく手足がしびれる場合
首の痛みとともに手や足のしびれがあるとすれば、神経の圧迫が起きている可能性が大きいです。症状が進むと、あるいはケガなどで急激な神経の圧迫が起こると手足に麻痺が現れることもあります。手足の感覚がない、うまく動かせないなど麻痺の症状がある場合は至急、受診してください。
麻痺はなく、しびれだけという場合でも、日常生活への影響は少なくないでしょう。たとえば、箸が使いにくい、服のボタンを留めるのに時間がかかる、さらに、ちょっとした段差にもつまずいてしまうなど危険を伴うこともあります。さらに、圧迫している神経によっては、便意や尿意がわからないなど排便や排尿の問題が起こることもあるので注意が必要です。首の痛みとともに手や足のしびれや麻痺があるという人は、早めに受診することをおすすめします。
首が痛いときはどんな検査をするか
首の痛みについて診断するときは、いつから、どういうときに痛いのか、また、痛みは急激か、徐々に増強しているか、痛みのほかに気になる症状があるかなどを確認します。さらに、今までにかかった病気、仕事の内容やパソコンに向かう時間など日常生活についても尋ねられるでしょう。
首が動く範囲(可動域)
自分で頭をどの程度、動かせるか、医師が手で動かしたときにどの程度、スムーズに動くか、また、動かしたときの痛みやしびれの有無、程度などを確認します。
神経学的検査
触覚などの知覚や反射などを確認し、神経の働きに異常がないかを調べる検査です。手を握ったり、開いたりできるか、また、握力などの筋力の低下や左右での違いなどを確認します。
画像検査
首が痛いときに行う画像検査として多いのはエックス線撮影です。また、脊髄を圧迫している可能性が高いときは、MRIなどを用いて精密検査を行います。MRI検査は磁気を利用した画像検査で、体を輪切りにした鮮明な断層画像を撮れるのが特徴です。
血液検査
感染症や炎症などが原因となって「首が痛い」という場合もあります。そのため、血液検査を行い、感染症にかかったときや炎症を起こしているときに増加する白血球や炎症などがあると陽性を示すCRPなどを調べます。
首が痛いときに自分でできる対処法
首の痛みを軽くするために必要な「姿勢の点検」
首が痛いというときに、見直してほしいのは「姿勢」です。たとえば、自分が立ったとき、パソコンに向かっているとき、スマホに熱中しているとき、どんな姿勢になっているでしょうか。
自分の姿勢は「何となく姿勢が悪い気がする」「猫背気味だと思う」などの自覚があっても、実際に鏡で見る機会は少ないものです。まして、写真を撮って見ることはほとんどないでしょう。しかし、普段の姿勢を確認するには、意識していないときにスマホなどで写真を撮ってもらうことをおすすめします。また、街を歩いているときも、ショーウインドーなどに映った自分の姿を確認してみるとよいでしょう。
姿勢を正す意識を持ち続けて習慣に!
猫背などの良くない姿勢を直そうとしても、つい、普段の状態に戻ってしまいます。一度、癖になった姿勢を直すには「意識を持ち続けること」が大切です。首~背中~骨盤が横から見たときに一直線になるように姿勢を正しましょう。猫背になっていたらその都度、姿勢を正す。その繰り返しの中で、体が良い姿勢を覚えられるようにしてください。
首の痛いところに湿布を貼って症状緩和
湿布薬は首だけでなく、関節の痛みがあるときよく使われますが、湿布には冷湿布と温湿布があります。使い分けの目安としては、痛みがでて間もない時期や痛いと感じる場所が熱い(熱感がある)、動かせないほど痛いというときは冷湿布がおすすめです。寝違えて首が痛いときは炎症が起きている可能性があるので、首を冷やす方がよいでしょう。
逆に、熱感がなく、長期に痛みが続いている場合は一般的に温湿布を貼ると痛みが緩和します。湿布のように貼るタイプのほかに、塗るタイプもあるので使いやすい方を選ぶとよいでしょう。
首が痛いときにはお風呂でリラックス
首の痛みで動かせないときや痛くなり始めたときにお風呂に入り、体が温まると痛みが強くなる可能性があります。しかし、筋肉がかたくなって首に痛みがでているときは、ゆったりと湯船につかるなど体を温めると痛みが和らぐことが多いです。
ぬるめの湯にゆったりつかると自律神経のうち副交感神経がよく働くようになり、リラックス効果も期待できます。ストレスの影響で首が痛いという人にも入浴はおすすめです。
市販の鎮痛薬で首の痛みを軽くする
首の痛みを和らげるには市販の鎮痛薬を服用するのも一つの方法です。薬剤師のいる薬局で症状を伝えて、自分に合う薬を選んでもらいましょう。
ただし、湿布や痛み止めなどの対処法は一時的に症状を緩和するだけで、根本的な問題を改善している訳ではありません。痛みが続くときは自分で対処するのではなく専門家に診てもらい、適切な治療を受けることが大切です。
首が痛いときにやりがちな自己流ストレッチに注意!
筋肉のコリが原因で首に痛みがあるときは首をゆっくり回したり、傾けたり、また、肩甲骨を大きく動かすと首の痛みが楽になることがあります。しかし、首をグルグル回す、反動をつけて激しく動かすなど過度な運動は、むしろ症状を悪化させる原因になるので注意が必要です。特に「首を動かすと痛い」という人が無理に首を動かしたり、ゴリゴリとマッサージしたり、自己流のストレッチをするのは止めましょう。
首のストレッチは「ゆっくり・やさしく」がポイントです。できるだけ安全で効果的なストレッチをするには、病院で医師やリハビリの専門家に正しい方法を教えてもらい、自宅で継続するとよいでしょう。
首が痛いという状態を防ぐにはどうしたらいい?
猫背など首に負担がかかる姿勢に注意する
自分でできる対処法でもお話ししたように、首の痛みを予防するために大事なことは、首だけではなく背中や骨盤も含めて姿勢を正すことです。「猫背になりがち」など自分の癖を知り、意識して背筋を伸ばしましょう。
また、同じ姿勢を長時間、続けないことも大事です。たとえば、30分ほどたったら休む、一度、立ち上がるなど意識的に姿勢を変えるとよいでしょう。
自分に合った枕選びで「首が痛い!」を予防
朝、起きたときに首の痛みが起こりやすい人は枕が合わず、首の負担が大きくなっている可能性があります。就寝中の首の角度は、横から見たときに体の線に対しておよそ15度にすると首の負担が少ないそうです。そのため、首の角度が15度程度になるように枕の高さ調整をしましょう。また、横向きに寝たときに首の負担が少ない枕は、頭(顔)の中心線と背骨の線が一直線になる高さとされています。
枕は長く使っていると高さが変わってくることもあります。今、使っている枕の高さが合っているか、早速、確認してみませんか。
姿勢を整えるには適切なメガネを使う
「最近、目が悪くなった」「メガネの度が合わなくなった」と感じている人はパソコンの作業をするときの姿勢に注意しましょう。画面を見ようとして、つい前かがみになって顎を突き出していないでしょうか?顎を前に突き出すと、首を後ろに反らす格好になるので首の痛みにつながります。首が痛いという困った事態を防ぐには、現在の視力に合ったメガネを使いましょう。
名医検索サイトクリンタル
名医検索サイトクリンタルでは日本全国の約30万人の医師から厳選された名医だけを掲載しております。手術数や外来の待ち時間など、受診する名医を決めるために必要な詳細情報を掲載しておりますので、受診先を検討される際の参考にしてください。
「どの名医に治療をお願いすればよいのかわからない!」とお悩みの方には、クリンタルの名医紹介サービスをお勧めしています。クリンタルが独自に厳選した「3,500人の有数の専門医」「35,000人の街の名医」の中から、あなたの病気/症状やご希望を考慮して、クリンタルの医師が最適な名医をご紹介します。