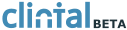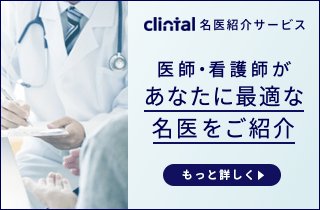インフルエンザは発症していないくても感染力がある潜伏期間に要注意!
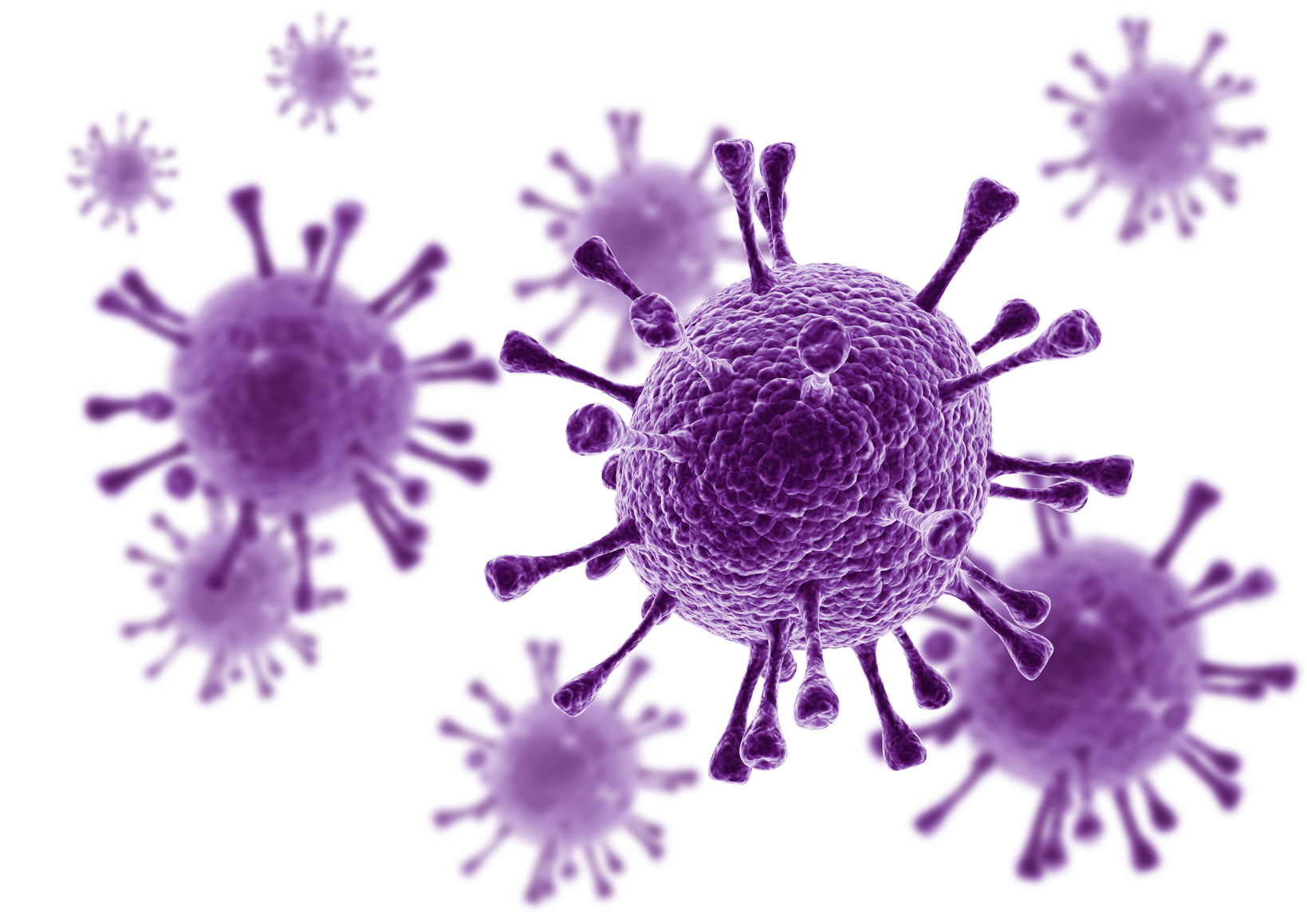
インフルエンザの潜伏期間はどのくらい?
インフルエンザは、かぜ(感冒)と同じように咳や鼻水、喉の違和感(咽頭痛)などの呼吸器症状が現れます。しかし、インフルエンザはかぜとは違い、突然の高熱に加え、頭痛や関節痛、また、全身倦怠感などの全身症状が早い時期に、しかも非常に重くなる傾向があり、感染力も強いことが特徴です。
インフルエンザなどの感染症は感染後、すぐに症状が出現するのではなく、潜伏期間というある程度の期間を経てから現れます。潜伏期間は症状としては出ていませんが、すでにウイルスには感染していて、体の中でウイルスが増え始めている時期です。
驚異的な速さで増えるインフルエンザウイルス
インフルエンザを引き起こす「インフルエンザウイルス」が鼻や口などから体に入り、体内では細胞内に侵入して増殖することによって高熱などの症状を引き起こします。
ウイルスは自分だけで増殖することはできず、細胞内に入り込み、そこで自分の遺伝子を複製(コピー)して増えていきます。インフルエンザウイルスの遺伝子(RNA)は人の遺伝子(DNA)に比べ、複製をする際に間違いが起こりやすく、変異しやすいという特徴があります。インフルエンザウイルスはわずかな「変異」(小変異、マイナーチェンジ)と「増殖」を繰り返すことで、やがてフルモデルチェンジといわれるほどの大変異を起こして新たなウイルスになっていくのです。
また、体に入ったインフルエンザウイルスはわずか20分ほどで細胞内に入り込み、8時間ほどたつと少なくとも100倍に増え、24時間がたつ頃には100万倍以上になるといわれています。インフルエンザウイルスの増殖するスピードは、まさに驚異的な速さです。
インフルエンザの潜伏期間は極めて短いことが特徴!
インフルエンザの場合、インフルエンザウイルスが「100万個以上」になった頃に症状が現れるといわれています。増殖スピードには個人差もあり、感染から発症するまでの時間は早い人ではおよそ16時間、遅い人では5~7日ほどで、症状が出現する時期としてもっとも多いのは感染から2~3日です。そのため、インフルエンザの潜伏期間は「通常、1~3日」とされています。
この1~3日という潜伏期間は、麻疹(ましん)、いわゆる「はしか」の潜伏期間(10~12日)や結核の潜伏期間(4~8週間)などに比べると非常に短いといえるでしょう。
そもそもインフルエンザはどのように感染するのか?
インフルエンザは「空気感染」することもありますが、主な感染ルートは「飛沫(ひまつ)感染」と「接触感染」です。
インフルエンザの感染ルート
・飛沫感染
咳やくしゃみをしたときには気道内の分泌物が飛び散りますが、この小さな水滴(小粒子)は「飛沫」と呼ばれています。ウイルスに感染した人が咳やくしゃみをすると、飛沫にはウイルスが含まれているので感染した人との距離が2メートルほど離れていても飛沫が届いて感染することもあるのです。
くしゃみで排出される飛沫は大きい粒子でも1~1.5メートル先にいる人に届き、その人の口や鼻、目の粘膜などから入り込んで感染する可能性があります。なお、一回の咳で飛び散る飛沫の数はおよそ10万個、くしゃみの場合は200万個ほどになるそうです。
・接触感染
インフルエンザに感染した人が咳やくしゃみをするときに手を当てると、ウイルスが手についてしまいます。その手で他の人の手に触れたり、ドアノブを触ったりするとそこにウイルスが付着して他の人にウイルスがうつり、感染することが少なくありません。
手で触れたところに限らず、飛び散った飛沫が机などのテーブルについていることも多いです。このようにウイルスなどの病原体が付着したものに触れて、手にウイルスがついて感染することを接触感染と呼んでいます。手すりやつり革、また、スイッチや電話、便座なども接触感染の原因になるのでまめに手を洗ったり、清掃を心がけたり、ウイルスを極力少なくすることが大切です。
・空気感染
咳やくしゃみで飛び散る飛沫は水分を含んでいますが、飛沫が乾燥すると床などに落ちる速度が遅くなるので長時間、空気中に漂うことになります。そのため、閉め切った部屋など気密性が高い環境にいると、空気中に浮遊するウイルスを含んだ飛沫を吸い込んで感染することもあります。
乾燥しているとインフルエンザにかかりやすい?
インフルエンザウイルスは「低温」で「乾燥」している環境では感染力が長く続き、感染が起こりやすいといわれています。日本で冬場にインフルエンザが流行するのは気温が低く、湿度も低く乾燥しやすいことが影響しているようです。
乾燥した環境では飛沫から水分がなくなって浮遊時間が長くなるだけでなく、喉の粘膜も乾燥して傷みやすくなるでしょう。喉の粘膜が荒れてしまうなど適切な状態に保てなくなるとインフルエンザウイルスにとっては侵入しやすい状態となり、感染しやすくなります。インフルエンザの予防として室内を適度な湿度(50~60%程度)に保つようにいわれるのは、このような理由があります。
インフルエンザの潜伏期間はウイルスの種類で違う?
インフルエンザは数多くの種類がありますが、人に感染するものに限るとA型、B型、C型の3つです。インフルエンザウイルスは、種類によって潜伏期間に違いがあるのでしょうか。
A型インフルエンザは感染力が強くもっとも危険!
毎年、流行する「季節性インフルエンザ」はA型によって起こします。A型は変異しやすく、3つのウイルスの中でもっとも増殖が速く、感染力が非常に強いことがA型の特徴です。インフルエンザの症状が出現する時期としては感染後2~3日が多いとされていますが、A型の場合は増殖スピードが極めて速いので症状が早い時期に出現し、潜伏期間が短くなる傾向があります。
ワクチンによる予防接種があるのはA型とB型
C型インフルエンザは季節を問わず感染しますが、感染しても鼻かぜのような症状で治まり、感染するのはほとんどが5歳以下のお子さんです。現在、行われているインフルエンザの予防接種はC型を除く、A型とB型のみです。予防接種の効果としては、変異の少ないB型に比べてA型は変異しやすいのでワクチンによる予防が難しいといわれています。
大流行した新型インフルエンザもA型?
B型は、人だけに感染が認められているウイルスですが、A型は鶏や豚、馬などの動物にも感染するウイルスです。しかし、ある特定の動物に感染するだけだったA型のウイルスが、小変異を繰り返して人に感染することがあります。それが、新型インフルエンザです。
新型インフルエンザといわれるウイルスは、本来、鳥だけ、豚だけといった特定の動物に感染するはずのインフルエンザウイルスが人にも感染するようになったもので基本的にA型ウイルスとされています。
インフルエンザの潜伏期間は年齢によって違う?
インフルエンザウイルスは、自分だけでは生存することも増殖するもできません。ウイルスが生存し、増殖するには他の生物の細胞に取りつき、侵入することが不可欠です。ウイルスのように他の生物に寄生する生物は、寄生する相手(宿主、しゅくしゅ)がそのウイルスの繁殖に適しているかどうかが増殖スピードに大きく影響するといわれています。
年齢によってインフルエンザの潜伏期間は変わる?
免疫力が低下した人は、ウイルスに対抗する力が弱いのでウイルスにとっては繁殖しやすい環境といえるでしょう。そのため、高齢者や幼いお子さんはインフルエンザにかかりやすく、重症化しやすいので注意が必要です。
高齢者の場合、特に注意したいのは感染しても症状がはっきりしないことです。インフルエンザにかかると典型的な症状としては38~39℃の高熱がでますが、高齢者は必ずしも高熱とは限りません。体温は普段と変わらないか、逆に低いことさえあります。そのため、インフルエンザの感染に気づくまでに時間がかかり、気づいたときには重症になっていることも多いのです。高齢者もインフルエンザの潜伏期間は1~3日と考えられますが、症状に気づくのが遅くなるという傾向があるので気をつけましょう。
また、お子さんの潜伏期間も、大人と同じように1~3日ほどといわれていますが、子どもの方が短期間で発症する傾向がみられ、1日程度で症状が出現することも少なくありません。5歳以下のお子さんは、C型インフルエンザのように大きくなった子どもや大人がかからないようなウイルスにも感染する可能性があるので注意してください。
感染のタイミングでインフルエンザの潜伏期間に違いが?
インフルエンザに感染したタイミングがインフルエンザウイルスの増殖速度に影響するという指摘があります。夜、寝る前に感染した場合と昼間、感染した場合を比べると夜の感染の方がウイルスの増殖が速いそうです。
また、体内リズムが乱れている人は感染のタイミングが昼間か夜かに関係なく、ウイルスの増殖スピードが速まるという意見もあります。夜更かしなど不規則な生活や夜勤などの影響で体内時計がうまく機能しない場合はインフルエンザウイルスの増殖が速くなり、潜伏期間の短縮につながる可能性があるようです。
インフルエンザの検査をすれば潜伏期間でも必ずわかる?
インフルエンザが潜伏期間にも人にうつす可能性があるとすれば、潜伏期間のうちに感染したかどうかを知りたいですね。しかし、残念なことに潜伏期間に検査しても、多くは意味のない検査になってしまいます。それは、どうしてなのでしょうか。
インフルエンザではどのような検査をするのか
インフルエンザの診断では現在、現れている症状のほかに、インフルエンザウイルスの有無を調べる検査などを行い、他に似たような症状を現す病気ではないことを確認した上で総合的に判断します。
インフルエンザの検査に使うのは「迅速診断キット」と呼ばれる検査用のキットです。鼻の中(鼻腔)を綿棒でこすったり、検査用の紙で鼻をかんだりして鼻の粘液や鼻水などを採ってインフルエンザウイルスの「抗原」を確認します。抗原は体にウイルスなどの異物が入ったときに免疫反応を起こさせ、異物の排除に役立つ「抗体」をつくらせる働きをもつ物質です。
インフルエンザの検査ではウイルスの「表面抗原」と呼ばれるたんぱく質でできた物質の量(抗原量)を測定し、感染の有無を判定します。検査で確認できるのはインフルエンザのA型とB型で、検査に必要な時間は10~15分ほどです。
感染していてもすぐに「陽性」にならない
インフルエンザに感染した場合、症状が現れるまでに時間がかかりますが、感染の有無を迅速診断キットで正しく判定できる状態になるにもやはり時間が必要です。感染したことを示す「陽性」になる割合(陽性率)は高熱などの症状が現れて3時間以内では50%未満ですが、7~12時間ほどたつと80~90%に上昇します。
感染後、抗原が増えるまでには時間がかかるため、潜伏期間や発症後の間もない時期は抗原が十分な量に増えていないことが多く、たとえ感染していても検査では陽性にならないのです。
また、粘液などの採取方法の違いによって陽性率が変わり、鼻の粘液を綿棒でこすって採取する「鼻腔こすり液」がもっとも精度が高いといわれています。しかし、小さなお子さんは鼻腔をこするのをとても嫌がるので、鼻をかむ方法や喉の奥(咽頭)をこする方法に変えると精度がやや下がってしまい、早期の正しい判定が難しくなることもあります。
名医検索サイトクリンタル
名医検索サイトクリンタルでは日本全国の約30万人の医師から厳選された名医だけを掲載しております。手術数や外来の待ち時間など、受診する名医を決めるために必要な詳細情報を掲載しておりますので、受診先を検討される際の参考にしてください。
「どの名医に治療をお願いすればよいのかわからない!」とお悩みの方には、クリンタルの名医紹介サービスをお勧めしています。クリンタルが独自に厳選した「3,500人の有数の専門医」「35,000人の街の名医」の中から、あなたの病気/症状やご希望を考慮して、クリンタルの医師が最適な名医をご紹介します。