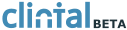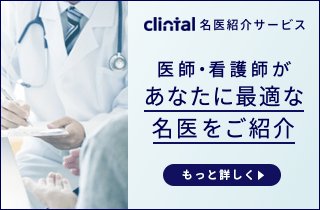傷の見えない手術!?名医による胆のう炎に対する腹腔鏡手術とは

胆のう炎には急激に腹痛や発熱が起きる急性胆のう炎と症状が長期間継続する慢性胆のう炎があります。どちらも胆石を伴っていることがほとんどで、再発しやすく放っておくと命に関わることもあるので手術を勧められることが多いです。今回は胆のう炎とその手術方法、特に腹腔鏡手術についてと、名医の見分け方について分かりやすくまとめます。
胆のう炎の腹腔鏡手術はどのような手術か
胆のう炎とは
胆のうは肝臓の下にある袋状の臓器で、肝臓から分泌された胆汁を一時的に溜めておく機能があります。胆汁は脂肪の分解を助けます。胆のう炎の原因の95%以上は胆石とも言われており、腹痛、発熱、嘔吐などの症状が起きます。
胆石によって胆汁の流れがせき止められてしまい、胆嚢が腫れ、放っておくと破裂、癒着、穿孔などを起こすことがあります。採血検査、超音波検査やCT検査などの画像検査などを併せて診断します。
細菌感染を伴うことが多く、血液を介して全身に細菌が回り敗血症を引き起こし命に関わる可能性もあるので、手術に耐えられる全身状態の場合には早めの手術を勧められます。手術には開腹手術と腹腔鏡手術があり、炎症のある胆のうを摘出します。胆のうを摘出しても、肝臓で分泌された胆汁はそのまま腸へと流れていくので体には問題ありません。
腹腔鏡手術とは
腹腔鏡下手術とは、お腹に「腹腔鏡」という細長いカメラを入れ、お腹の中の様子をテレビのモニターに映しながら、行う手術のことです。お腹の中をモニターで確認しつつ、鉗子という細長い器具を使って行う手術です。イメージは、細長い高枝切りばさみのような器具を想像していただけるとわかりやすいと思います。
腹腔鏡手術による胆のう炎の手術は、おへその下の部分を約2cmほど切って、そこから腹腔鏡を入れます。一般的には、みぞおちに1箇所、右側の肋骨の下に2個所の、合計3個所に小さな穴を開け、そこから鉗子を上手に使って胆のうを取り出すことになります。
胆のう炎に対して腹腔鏡手術を選択するケースとは
それでは、名医は胆のう炎に対する治療方針をどのように立てるのでしょうか。重要になるのはベストな治療法を見極める前に、まずは症状を完璧に把握することです。
そのためにまずは点滴や抗生剤などで炎症を抑えながら、手術に耐えられる全身状態かどうか、具体的には血圧が安定しているか、肺や心臓、腎臓などの機能に問題はないかなどを判断します。血液検査も併用し、胆のう炎の炎症による全身への影響も把握します。
手術方法の種類
手術方法には開腹手術と腹腔鏡手術がありますが、経験症例数の多い名医であればなるべく腹腔鏡手術を選択します。その理由は傷が小さいため術後の疼痛が少なく、回復も早いので早期の退院が望めるからです。また美容上も傷が少ない方が患者さんにとっては良いと考えられています。
従来の胆のう炎に対する腹腔鏡手術はお腹に3-4か所穴を開けて、お腹に空気を入れてカメラ(腹腔鏡)で観察しながら胆のうの摘出を行いますが、最近では単孔式腹腔鏡手術といってお臍に開ける1つの穴だけで腹腔鏡手術を行う方法もあります。この方法だと、腹腔鏡手術をした傷はお臍に隠れてほとんどわからないと言う利点があります。
しかし、単孔式腹腔鏡手術は1つの穴から腹腔鏡や複数の手術器具を挿入するので従来の腹腔鏡手術より高度な技術が必要です。腹腔鏡手術の経験症例数の多い名医でないと施行できない手術方法と言えます。
胆のう炎の腹腔鏡手術の長所
先程、腹腔鏡手術は傷が小さく、術後の疼痛が少なく、回復も早い、と書きましたが、それ以外にも長所はありますのでまとめておきます。
開腹手術と比較すると、
- 傷が小さく美容上優れている
- 創が小さいため痛みが軽い
- 翌日から飲水や食事が可能である
- 早期退院ができるため早期の社会復帰が可能である
- 入院期間が短いため経済的に優れている
など多くの点でメリットがあります。このように多くのメリットがあるからこそ、開腹手術よりも先に、第一選択として腹腔鏡手術が適用可能か検討されるわけです。
実際に腹腔鏡手術で胆のうを摘出した後に、どれくらいの期間で退院できるかというと、合併症が怒らなければ2−3日で退院することが可能です。
胆のう炎に対する腹腔鏡手術の後遺症や合併症
手術となると、どんな手術でも合併症やリスクが気になりますよね。
そもそも胆嚢摘出術は、後遺症や合併症のリスクの低い手術といわれています。日本消化器病学会の「胆石症診療ガイドライン」によると、1990年から2005年までの15年間、254,205例の手術において、合併症が起こったのはわずか5%ほど(10,321例)と報告されています。これは軽微なものも含んでおり、そのうち重大なものは0.01%以下(22例)であったことが報告されています。これらのことを踏まえると、比較的安全な手術と言えるでしょう。
胆嚢摘出手術の後遺症や合併症の種類
胆嚢摘出術の合併症は手術中の合併症と手術が終わったあとの後遺症に分けられます。
手術中の合併症
- 出血
- 胆管の損傷
などが挙げられます。多くの場合、癒着がひどい症例で起こります。
手術後の合併症
- 出血
- 傷口からの感染
- 胆汁が漏れ出る
- 肩こりに似た肩の痛み
- 脂っこい食事を摂取したときに下痢になりやすくなる
ここで書きました、「肩の痛み」や「下痢の発生」といった症状は、3ヶ月ほどすれば、多くの場合改善されます。退院後は、基本的には普通に生活していれば問題ありません。
名医は胆のう炎に対し必ず腹腔鏡治療を選択するのか
それでは名医は胆のう炎に対し必ず腹腔鏡手術を選択するのでしょうか。確かに腹腔鏡手術の方が開腹手術に比べて利点は多いですが、目で直接見ることのできる開腹手術の方が出血のコントロールや創部の観察は容易です。なんでもかんでも腹腔鏡手術にこだわるのも、また名医とは言えません。腹腔鏡手術も開腹手術も十分な経験があるうえで、患者の症状や病態を見極めて、どの手術がベストなのかを冷静に判断し、複雑な処置が予想されるときにはあえて腹腔鏡を選択しないという判断もすることができるのが名医の条件なのではないでしょうか。
また、ほとんどの病院の手術説明文書には、腹腔鏡手術を予定しても手術中に開腹手術に切り替わる可能性について書かれています。手術中の患者の容態や、想定できなかった要因によって腹腔鏡手術を継続するとリスクが高くなると判断した場合には、手術の方法を変えることもあるわけです。できれば腹腔鏡手術で治療が完了すると良いですが、その時の状況で最も良い治療を選択できる医師こそ名医と考えられます。
もちろん名医であれば、そうした要素を極力排除するために、検査を入念に行い、予定通りに手術を行うことができることも多いのですが、手術においては「絶対」はないと言われるため、冷静な判断で患者さんの治療を常に最優先に考えられることが最も重要です。
また、単孔式腹腔鏡手術に関してはより高度な技術が必要なため事前の検査で適応となるかどうか的確に判断しなくてはいけません。
胆のう炎の腹腔鏡手術の前に必要な検査
腹腔鏡手術が適応となるかどうかを調べるために、いろいろな検査が必要となります。必要な検査は、基本的には手術の前に外来通院で行います。これはなるべく入院期間を短期間とするためです。
検査項目は一般的に、
- 血液検査
- 心電図検査、胸部・腹部レントゲン検査、肺機能検査
- 超音波検査
- CT検査
- 胆管造影検査
- 胃内視鏡検査
などです。
これらの検査を主な検査として、その結果によっては追加の検査が必要になる場合もあります。
また最近は高齢化社会ということで、患者さんの年齢が高齢化しているということもあり、他に色々な治療中の病気を持っている患者さんも多くいらっしゃいます。そのような患者さんに対しては、消化器外科だけでなく、他の関連する診療科に診察を依頼し、より安全に手術を行うための準備も心がけています。
胆のう摘出の腹腔鏡手術における名医の見分け方
クリンタルで名医がいる施設として紹介している東邦大学医療センター大橋病院 肝胆膵外科のホームページには、年間150例を超える胆のう摘出における腹腔鏡手術を行っていると明記してあり、腹腔鏡手術が難しいとされる手術既往歴がある患者さんや、高度炎症例に対しても適応としています。
しかし開腹手術移行率は5%前後と他施設と相違ないということは、高い技術がある名医によって手術が行われていると考えられます。同施設ではもちろん、単孔式腹空鏡手術も行われています。
胆のう炎に対する腹腔鏡手術を希望し名医を選ぶときには、年間の手術症例数や適応症例、開腹手術移行率などについて注目してみると良いかもしれません。
【併せて読みたい】
開腹手術 vs 腹腔鏡手術ー知っておくべき治療法①
こちらのコラムでは、開腹手術と腹腔鏡手術のメリット・デメリットについて比較しています。
「どの名医に治療をお願いすればよいのかわからない!」とお悩みの方には、クリンタルの名医紹介サービスをお勧めしています。クリンタルが独自に厳選した「3,500人の有数の専門医」「35,000人の街の名医」の中から、あなたの病気/症状やご希望を考慮して、クリンタルの医師が最適な名医をご紹介します。