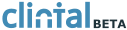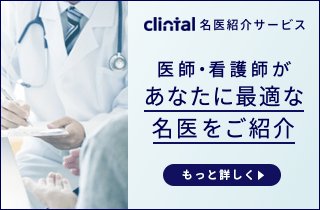親知らずの抜歯を口腔外科でやることを勧められた…親知らずはどうなってるの?

親知らずは、困ったことにまっすぐはえてくることも少なくない歯です。しかも、大きさもおおぶりな歯であることが多く、とても抜きにくい歯でもあります。そのため、一般の歯科から口腔外科に抜歯を依頼される傾向にあります。そこで、口腔外科での親知らずの抜歯についてまとめてみました。
親知らずってなに?
親知らずは、正式には第三大臼歯とよばれる最も奥にはえてくる歯です。智歯とも言います。親知らずがはえてくる時期は、もう親が子どもの口の管理をしているような年齢ではありません。そこから、「親が知らないうちにはえてくる」ということで、親知らずとよばれる様になったといわれています。
通常は、歯がはえるとともに顎の骨も成長し大きくなっていきます。しかし、親知らずがはえてくる時期は、成長が終わっている年頃になります。そのために、親知らずが生えてくる前に、親知らずの手前にある第二大臼歯の後ろ側に十分なスペースが出来ていないと、親知らずがはえてくる余地が残されていないことになります。親知らずが、なかなかまっすぐはえてこない場合が多いのは、こうした理由によります。
親知らずの検査
親知らずの抜歯を行なう前に検査が必要となります。特に必要な検査は、レントゲン写真撮影による検査です。この場合は、パノラマX線写真とよばれる口全体を写す検査をまず行ないます。これにより、親知らずの形、位置、向き、そして親知らずの周囲の歯や骨との関係を調べます。特に大切なのが、下顎の親知らずを抜歯する場合で、下顎管とよばれる神経や血管の通っている管との関係です。上顎の抜歯の場合は、上顎洞とよばれる鼻の横にある大きな空洞との関係になります。
また、必要に応じて、CTを撮影することもあります。CTを撮影すれば、親知らずのより正確な情報が得られます。例えば、パノラマX線写真でわかるのは、向きについては前後方向への傾き具合だけですが、内側への傾きもわかる様になります。また、親知らずの根の状態も正確につかむことが出来ますので、パノラマX線写真だと1本だと思っていたけれど、CTを撮影したら細い根がもう1本みつかったというようなことがあります。
口腔外科で抜いた方が良い親知らずの特徴
下顎の親知らずの場合
レントゲン上、下顎管に親知らずの根の先が近い場合は口腔外科で抜いた方が良いでしょう。根の先が近いということは、下顎管の周囲の骨が薄いということを意味しています。抜歯の時に、この骨の薄いところを傷つけてしまうと、下顎管の内部を走っている神経をしびれさせてしまう可能性があるからです。また、神経と同時に血管を損傷しますと、大出血をきたすこともあります。こうしたことが予想される場合は、口腔外科で抜歯を受ける方が良いでしょう。
また、親知らずの埋まっている位置がとても深く、抜歯するためには骨をたくさん削らなければならない様な場合や、下向きに埋まっている様な場合も、口腔外科で抜いてもらう方がいいです。
上顎の親知らずの場合
上顎の親知らずの場合は、上顎洞の底と親知らずとの位置関係が重要になってきます。上顎洞とは、鼻の横、目の下にある骨の空洞です。上顎洞の底にあたる部分の骨が薄くなっている際に上顎の親知らずを抜くと、上顎洞の底に穴が開いてしまうことがあります。小さな孔であれば自然に塞がりますが、大きな穴が開いてしまった場合は、穴を閉じる処置をしなければなりません。
ですので、レントゲン写真で上顎洞の底の部分の骨が薄くなっているなら、口腔外科での抜歯をお勧めします。上顎の親知らずが深い位置に埋まっている場合、抜歯をした時に上顎洞の底の骨を突き抜けて、上顎洞内部に親知らずが入り込んでしまうことがあります。もし入り込んだ場合は、取り除く処置を行わなければなりません。親知らずがレントゲン上、深い位置に埋まっているときも口腔外科で抜歯を受ける方がいいでしょう。
口腔外科に依頼されるような親知らずの抜歯の方法
口腔外科に抜歯を依頼される様な親知らずは、倒れて埋まっている場合が大半です。このような親知らずを「水平埋伏智歯」といいます。水平埋伏智歯の抜歯は、通常の抜歯と異なり切開、骨や歯を削る、縫合などの工程が必要となり、難易度は高くなってきます。
①麻酔
麻酔は、ほぼ局所麻酔で行なうと思ってください。意識のない状態にする全身麻酔で抜歯することはないことはないですが、基本的に稀です。抜歯する親知らずの周囲の歯茎に麻酔の注射を行ないます。なお、伝達麻酔とよばれるより広範囲に効く麻酔を行なうこともあります。
②切開
親知らずが埋まっている場合、親知らずの頭の部分を覆っている歯茎を切開します。そして、親知らずの頭の部分をしっかりと露出させます。
③骨削除
親知らずの頭の部分が骨に埋もれている場合は、その付近の骨を削り、親知らずの頭を出します。
④分割
横向きに親知らずが倒れて埋まっている場合、歯の方向に抜こうとしても手前の歯に当たるので、そのままでは抜けません。そこで、親知らずを削り、まず頭の部分を取り除きます。これを分割といいます。また、親知らずの根が太い、もしくは数本ある様な場合は、親知らずの根を削って小さくすることもあります。
⑤縫合
親知らずを抜歯したあとは、切開した歯茎を元の位置に戻し、縫って閉じます。このとき、止血剤を入れることもあります。
⑥投薬
化膿止めと痛み止めをセットで2〜3日、痛いときの追加分の痛み止めを5回分ほど処方します。
⑦抜糸
縫合した後の抜糸は、おおむね1週間後になります。
このように、親知らずの抜歯は、通常の抜歯とは異なる方法になりますので、水平埋伏智歯の抜歯は一般の歯科診療所ではなく、口腔外科で行なわれることが多くなっています。
抜歯後の注意事項について
口腔外科で親知らずを抜歯した場合、以下の様な注意点を守ってください。
食事の注意
局所麻酔がさめるのに、おおむね2〜3時間かかります。また、それ以上かかることもあります。麻酔がさめるまでの間は、食事は控えてください。頬や舌を噛んでも気がつかないので、思わぬケガをすることがあります。また、麻酔がさめた後の食事は、刺激の少ない軟らかいものを摂る様にしてください。
出血予防のための注意
抜歯後は、ガーゼを噛む様に指示される筈です。少なくとも30分は噛み続けてください。
当日の運動は控えてください
抜歯当日は、スポーツは控え、家で安静にしてください。
当日のうがいは控えめにしてください。
当日は、なるべくうがいを控えてください。食後の歯みがきは傷に当たらない様に行ない、その後のうがいは、優しく軽めに行なってください。
入浴はシャワー程度にしてください。
抜歯当日は、お風呂につからず、シャワー程度にしてください。
お酒やタバコ
お薬が出ている期間の飲酒は控えてください。また、タバコも傷の治りに影響しますので、控える様にしてください。
親知らずの抜歯後の経過について
腫れ
親知らずを抜歯しますと、腫れます。特に口腔外科に依頼される様な親知らずの場合はなおさらです。人によっては顔が腫れてしまうくらいになることもあります。この親知らずの抜歯後の腫れは、抜歯後24〜48時間をピークとして腫れていき、それからひきはじめます。この経過は、親知らずに限ったことではなく、さまざまな手術を受けた後の腫れの経過とほとんど同じです。そして、腫れることで、お口を開け閉めするための筋肉の動きが悪くなり、一過性にお口を開けにくくなることがあります。
あざ(皮下出血)
また、腫れとは別に、抜歯した付近に皮膚にアザができることがあります。深い親知らずの場合に起こることが多いです。アザもいずれはひいてきますが、腫れよりは長引きます。消えるまでにおおむね2〜4週間かかります。
痛み
親知らずを抜歯すると、麻酔が覚める頃から痛みを感じ始めます。しかし、ほとんどの場合、痛み止めの薬を飲めば痛みをおさえることが可能な程度です。
出血
抜歯後、30分ほどガーゼを噛んでもらえれば、ほとんどの出血は止めることが出来ます。ただし、抜歯後数日間は、唾液に血がにじむ様な出血は続くことが多いですが、にじむ程度であれば心配することはありません。
親知らずの抜歯後の偶発症について
上顎および下顎の親知らず抜歯に共通すること
- 抜歯後治癒不全(ばっしごちゆふぜん)
親知らずを抜歯した後、抜歯後治癒不全という痛みがなかなかひかない状態になることがあります。通常、抜歯したことで出来た穴は骨が露出するわけですが、この骨の表面から出血してきます。この出血した血液が、固まってかさぶたになり、抜歯で出来た穴を保護し、骨を覆ってくれます。こうして治していきます。
ところが、抜歯後治癒不全になりますと、このかさぶたが出来ません。そのために骨が露出した状態になります。血液で満たされず乾いた状態ということで、歯科医師はドライソケットとよぶこともあります。骨は本来露出するべきものではないので、露出したことによりさまざまな刺激にさらされます。この刺激が辛い痛みを引き起こすのです。痛みの緩和を口腔外科に依頼されることが多いのですが、抜歯後治癒不全に対する治療法は、現時点では確立されておりません。痛み止めや化膿止めの軟膏を詰めたりして対応していますが、各施設によって異なる対応になることが多いです。
- 抜歯後出血
親知らずを抜歯した後、血が止まったのを確認してから帰宅してもらうわけですが、帰宅した後に再び出血してくることがあります。この場合は、まずガーゼをまるめて30分ほど噛んでもらうと、ほとんどのケースで出血は止ってきます。もし、30分ガーゼを噛んでも血が止らない場合は、抜歯してもらった歯科医院に連絡してください。なお、唾液に血がにじむ程度の出血は、数日は続くことが多いです。
- 口角炎(こうかくえん)
親知らずはとても奥にあるので、大きくお口を開けてもらわないと抜歯が出来ません。抜歯を行なっている間、大きく開け続けることで、口の角の部分があれてしまうことがあります。
- カウザルギー
なかなか耳慣れない言葉だと思います。カウザルギーとは抜歯した後の異常感覚のことです。親知らずの抜歯に限らず、全身の他の部分の手術の後でも起こりえます。カウザルギーの症状は人によって異なります。焼ける様な痛みの場合もあれば、抜いた筈なのにむし歯の痛みがあるなど、さまざまです。頻度は非常に少なく50〜80万人に1人といわれています。この症状には、通常の痛み止めは効きません。麻酔科のペインクリニックとよばれるところで、特別な治療を受ける必要があります。
下顎の親知らず抜歯の際におこりうること
下顎の親知らずを抜歯した後に起こりうることとして、下顎神経や舌神経の麻痺があります。下顎の親知らずの下方に、下顎管とよばれる神経や血管の通り道があります。親知らずは、根が他の歯よりも深い位置になり、下顎管に近くなっています。そのために、抜歯後の腫れが下顎管を圧迫したり、親知らずを抜歯する際に下顎管を傷つけたりすることで、下顎管の中を通っている下顎神経が痺れてしまうことがあります。
下顎神経が痺れると、顎の先や下唇の感覚が鈍くなります。また、親知らずの内側に舌神経が走っています。こちらが痺れますと、舌の感覚が鈍くなります。もし、こうした神経の痺れ症状が現れた場合は、飲み薬を出して、症状の改善を図ります。
上顎の親知らず抜歯の際におこりうること
上顎の場合は、親知らずの上に上顎洞とよばれる空洞があるのですが、この空洞に関するリスクがあります。ひとつは、上顎の親知らずを抜歯したところ、親知らずの根の先に骨がなく、上顎洞と親知らずを抜歯して出来た穴がつながってしまうことです。こうなると、お口の中に含んだ水が鼻に流れ込んでしまいます。また、上顎洞の周囲の骨が薄い場合に、親知らずが上顎洞に落ち込んでしまうことがあります。
まとめ
親知らずは多くの人が抜歯が必要となります。口腔外科というと何かすごい手術をされそうで怖いですが、やはり危険性が高いと一般歯科で判断された場合には、怖がらずに口腔外科で抜歯してもらいましょう。
名医検索サイトクリンタル
名医検索サイトクリンタルでは日本全国の約30万人の医師から厳選された名医だけを掲載しております。手術数や外来の待ち時間など、受診する名医を決めるために必要な詳細情報を掲載しておりますので、受診先を検討される際の参考にしてください。
「どの名医に治療をお願いすればよいのかわからない!」とお悩みの方には、クリンタルの名医紹介サービスをお勧めしています。クリンタルが独自に厳選した「3,500人の有数の専門医」「35,000人の街の名医」の中から、あなたの病気/症状やご希望を考慮して、クリンタルの医師が最適な名医をご紹介します。