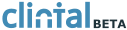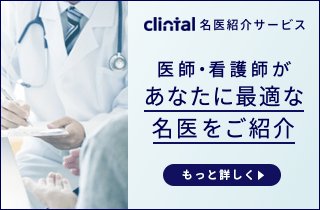「病診連携」の歴史
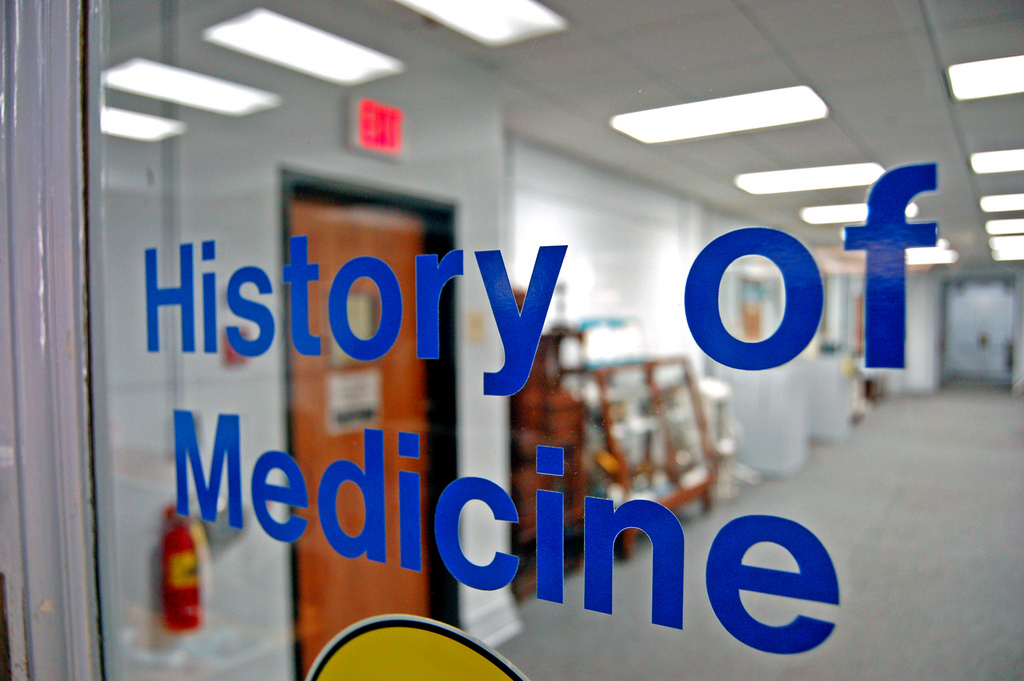
「病診連携」って何?
最近、「病診連携」という言葉を耳にする機会が増えてきたと思います。
「病診連携」とは、病院と診療所が各々の役割や機能を分担し、連携することを指します。この連携によって、より適切で効果的な医療の提供を目指しているのです。今回は、この「病診連携」というキーワードをもとに、日本の政策の歴史を振り返ってみましょう。
そもそも厚生労働省の資料によると、日本における医療提供体制は、次に挙げるような3つのフェーズで進んできました。
1945〜1985年:①医療基盤の整備と量的拡充の時代
1985年:第一次医療法改正
1985〜1994年:②病床規制を中心とする医療提供体制の見直しの時代
1992年:第二次医療法改正
1992年〜:③医療施設の機能分化と患者の視点に立った医療提供体制の整備の時代
1997年:第三次医療法改正
これらのフェーズの進行は、『医療法』の改正がターニングポイントとなってきます。
『医療法』とは医療界における最も重要なルールで、医療を受ける人々の利益を保護し、良質で適切な医療を効率的に提供する体制をつくることで、人々の健康の保持を目的とした法律です。
では次に、『医療法』の改正を経て日本の医療提供体制はどう変わってきたのでしょうか。
①医療基盤の整備と量的拡充の時代(1945~1985年)
戦後公布された日本国憲法にて社会保障が規定され、1948年には『医療法』が成立し、この法律によって、病院(20床以上)と診療所(19床未満)が明確に区分されました。この時点では、病診連携について特に規定されているわけではありません。
1980年代に入ると、老人医療費の無料化による社会的入院の増大(福祉施設に入所するよりも入院した法が安いため、医療機関に必要以上に長期間入院する)や、富士見産婦人科病院事件(無資格の理事長が超音波診断装置を操作し、根拠のない病名をでっちあげ多くの女性たちに不必要な手術を行うという残悪な事件)を受け、医療の提供体制に疑問が投げかけられるようになりました。
これをうけて1985年に第 一次医療法改正が行われました。
②病床規制を中心とする医療提供体制の見直しの時代(1985~1994年)
第 1次医療法改正では、医療法人に対する監督の強化と共に、「医療計画」で全国を 355の区画(2 次医療圏)に分け、それぞれの区画での病床数規制が盛り込まれました。
それでは、そもそも医療圏とは一体どのようなものでしょうか。
大まかに説明すると以下のようになります。
- 1次医療圏=基本的に市町村単位、身近な医療を提供する医療圏
- 2次医療圏=複数の市町村単位、一般的な医療サービスを提供する医療圏
- 3次医療圏=都道府県単位(除く北海道)、最先端・高度な技術を提供する特殊な医療を行う医療圏
つまり、2次医療圏ごとということは複数の市町村を1単位として全国を区分けし、それぞれの地域の病床数を規制したのです。猶予期間中の「駆け込み増床」という問題点はありましたが、この法改正を機に、量的拡充の時代から、質重視の時代に入ったといえるでしょう。
1990年代に入ると、高齢化が進み、よくみられる疾病に変化がみられるようになりました。そうなると、長期療養を必要とする高齢者のための医療施設機能の体系化が必要となりますし、医学の進歩に合わせた医療機関の整備のためにも、医療機関の機能を分化する必要性が謳われるようになります。
③医療施設の機能分化と患者の視点に立った医療提供体制の整備の時代(1992年〜)
上記を受けて、第 2 次医療法改正では、医療機関の機能を分化する制度が始まり、高度な医療を行う「特定機能病院」、長期療養を行う「療養型病床群」が制度化されました。以降、それぞれの医療機関の機能が明確になってきました。ついに患者の視点に立った医療提供体制の整備の時代が到来したと言えます。
1990年代後半に入ると、急速に進む高齢化に伴い、要介護者が増大、ますます医療機関の機能分化が重要視されるようになりました。
こうして第 3 次医療法改正(1997年)では、療養型病床群制度を診療所へ拡大するとともに、新たに地域医療支援制度病院を創設しました。これは、かかりつけ医等に対する支援として、紹介患者への医療提供、医療機器の共同利用や開放化、救急医療の提供、地域の医療従事者の研修などを行う病院のことです。地域医療の中心となる施設であり、かかりつけ医等への逆紹介も行います。
(※かかりつけ医:コラム「かかりつけ医の役割」参照)
このように、それぞれ医療機関に明確な役割・機能を持たせることで、軽症の人々が不必要に大病院に足を運ぶことに歯止めをかけ、症状に適した医療機関で、適切な医療を受けられる仕組みを作ろうとしているのです。
これからの日本医療
これまで、200 床以上の大病院に紹介なしで受診する場合、病院の定める初診料を自己負担で支払うこととし、大病院の外来受診を減らすよう経済的に誘導してきました。しかし、未だ軽症でも紹介状をもたずに大病院を受診する患者が多く見られます。
(※初診料:コラム「“初診料”-受診するって難しい①」参照)
そこで厚生労働省は、紹介状を持たずに大病院を受診した患者に対し、新たに負担金を求める制度を、2016年4月をめどに導入することを発表しました。
ここでのねらいも、まず患者が地元の「かかりつけ医」を訪ね、そこで大病院が必要か判断するよう誘導することで、効率的な医療提供を実現すること、医療費を軽減することに狙いがあります。
これからの日本の医療は、従来以上に「かかりつけ医」の重要性が増し、病診連携が欠かせないものとなってくるのです。
「どの名医に治療をお願いすればよいのかわからない!」とお悩みの方には、クリンタルの名医紹介サービスをお勧めしています。クリンタルが独自に厳選した「3,500人の有数の専門医」「35,000人の街の名医」の中から、あなたの病気/症状やご希望を考慮して、クリンタルの医師が最適な名医をご紹介します。