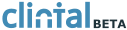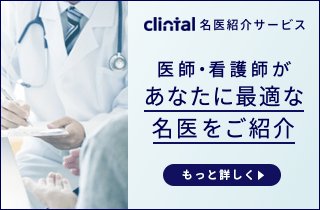めまいが続く原因は?軽視したら危険なめまいも!

めまいが続く…
突然、地面が回る、急に体がふらついてまっすぐ歩けないといったことが起きたら不安になりますね。めまいのほかに、耳鳴りや吐き気なども現れると、いったい何が起きたのかと心配になるでしょう。
めまいには一時的なものもありますが、ひどいめまいを何度も繰り返すものもあります。また、めまい自体は軽くても長期間、続くこともあるので日常生活への影響は次第に大きくなるでしょう。めまいの種類としては「グルグル」と回るような回転性めまいや「フワフワ」してふらつくような浮動性めまい、立ち上がったときに「クラッ」とするようなめまいがあります。
めまいは耳の異常によるものが多いといわれますが、原因はさまざまです。脳の働きや血圧に異常が起きた場合、あるいは重症の貧血や不整脈、さらに、ストレスや薬の影響なども考えられます。めまいの影響としては、体のバランスを保つための平衡感覚(へいこうかんかく)が乱れてしまうので倒れてケガをする可能性があります。もし、車の運転中なら一層、危険を伴うでしょう。脳梗塞や脳出血などに伴う脳の異常が原因であれば生命にかかわります。めまいが続くときは軽く考えずに、病院を受診して原因を確認することが大切です。
そもそもめまいが続くのはなぜか
普段、なかなか気づきませんが、人が姿勢を保つ、まっすぐに歩くというときには平衡感覚という体のバランス(平衡)を保つための機能が働いています。めまいが起こるのは、この平衡感覚がうまく働いていないためです。
体のバランスを保つときには耳や眼から入る体の位置や向きなどの情報、また、手足の関節や筋肉からの情報が平衡感覚を司る小脳や脳幹(のうかん)に伝わってまとめられます。脳幹は心臓の働きなど生命の維持にも重要ですが、体の平衡を保つ上でも役立っています。小脳や脳幹に伝えられた情報は体の関節や筋肉などに指令を与える大脳皮質に伝えられ、体のバランスをとっているのです。
しかし、片方の耳や眼に異常が起こると左右の感覚器から異なる情報が脳に送られることになり、また、脳の方に異常があれば体に適切な指令を出すことができません。このように体のバランスを保ちにくい状態になると、めまいを感じるようになります。
めまいのおよそ8割は耳の異常といわれますが、特に、内耳(ないじ)という耳の奥にある器官が関係していることが多いです。内耳のうち、耳石器(じせきき)と三半規管(さんはんきかん)の働きが障害されるとめまいを引き起こします。
耳石器は重力や加速度などを感じ取るところで、三半規管は半円形の3つの管が直角に交わり、体が動いている方向などを捉えている器官です。体を動かすと三半規管を満たしているリンパ液の流れが変わり、その変化を「体の動き」として脳に情報を送り、体のバランスを保っています。耳石器の障害では浮動性めまいが現れやすく、三半規管に障害が起こると回転性めまいを感じることが多いです。
めまいの原因にはどういう病気が考えられるか
めまいを起こす病気は耳の病気をはじめ、脳梗塞など脳の病気や起立性低血圧などの血圧変動、また、重い貧血などがあります。
耳の異常でめまいが続く場合
めまいを起こす耳の病気にはメニエール病や突発性難聴、良性発作性頭位めまいなどがあります。
メニエール病
内耳リンパの異常が原因で起こるメニエール病はめまいを起こす代表的な病気です。めまいと同時に難聴や耳鳴り、耳に物が詰まったような耳閉感などが起こり、吐き気や嘔吐、冷や汗などを伴うこともあります。メニエール病は40歳以上の壮年期に多く、回転性めまいと難聴、耳鳴りを繰り返すことが特徴です。めまいが続く期間は数週間から数か月、長いと1年以上ということもあります。また、難聴はほとんどが片方の耳に起こりますが、めまいの発作を繰り返すうちに高度の難聴となることもあるので注意が必要です。
突発性難聴
突発性難聴は、急に耳が聞こえなくなる病気です。メニエール病のようにめまいと難聴、耳鳴りが現れますが、突発性難聴は難聴と耳鳴りが中心でめまい自体は軽く、めまいが起こらない人もいます。原因としては内耳への血流不足やウイルス感染などが挙げられていますが、過労やストレスが発症に関係するといわれています。
良性発作性頭位めまい
耳の異常でめまいが起こるときに多いのが、良性発作性頭位めまいです。急に振り返ったり、寝返りをしたり、上半身を急に動かしたときに軽い回転性のめまいが起こります。体の傾きや重力などをキャッチする耳石器の異常と考えられていますが、頭部の打撲や慢性中耳炎なども原因の一つです。耳鳴りや聴力の低下などはなく、めまいも20秒ほどでおさまります。
脳梗塞など脳の異常で起こるめまいは
脳の中で体の平衡に関係する小脳や脳幹、また、情報が行き来する神経に異常が起こるとめまいが生じます。
脳卒中が原因でめまいが続く場合
脳梗塞や脳出血などのいわゆる脳卒中が小脳に起きたときは、めまいのほかに吐き気や嘔吐、頭痛や舌のもつれ、ふらつきなどが起こります。また、脳幹に梗塞や出血が起こると物が二重に見える複視、体の片側の感覚障害や顔面の麻痺、手足の動きが悪くなることも多いです。脳卒中が疑われるときは速やかに病院を受診してください。脳卒中のめまいの6~7割は浮動性めまいで、めまいが長く続く傾向があります。20~30分程度の場合もありますが、多くは数時間続くめまいです。
脳卒中の場合、注意してほしいのはめまい以外の症状は「めまいと同時とは限らない」ということです。たとえば、血管が詰まる梗塞が起きた範囲が狭いときは運動障害が軽いため見過ごされてしまうこともあります。次第に梗塞の範囲が広がり、めまいの後、数日して麻痺などの重い症状が現れるということもあるので注意しましょう。
その他の脳の病気が原因でめまいが続く場合
聴神経腫瘍は聴神経に良性腫瘍ができる病気です。初期には耳鳴りや難聴だけですが、腫瘍が大きくなるにつれて周囲の組織や神経を圧迫し、めまいや吐き気、顔面神経麻痺などが起こるようになります。
また、椎骨脳底動脈循環不全症によるめまいは、脳幹や小脳の機能低下によって起こるめまいです。脳幹や小脳に血液を送る椎骨脳底動脈が狭くなったり、圧迫されたりして血流不足が起こり、脳の働きが悪くなってめまいが現れると考えられています。めまいのほか、舌のもつれや複視、手や足のしびれなどが現れることがあります。
その他の原因でめまいが続くことも
起立性低血圧や貧血などの血圧や血液の異常もめまいを引き起こす要因の一つです。また、気分の落ち込みや意欲の低下などが起こるうつ状態でも身体的な症状が目立つこともあり、めまいが続くこともあります。
めまいがどれぐらい続くと病院の受診が必要か
めまいが続くときに、病院に行く必要があるのはどんなときかをご紹介しましょう。
高齢者のめまいに注意!脳の病気が疑われる場合
めまいは脳卒中が原因となっていることもあるので、軽視すると命にかかわるので注意してください。脳卒中が起きた場合はめまいのほかに体のしびれ、ろれつが回らない、足がもつれるなど感覚や運動にも症状が現れます。めまい以外に脳卒中の症状がみられるときは救急車を呼ぶなどして至急、受診してください。
脳卒中の経験がある人にめまいが続く場合
過去に脳梗塞などの脳の病気を経験したことがある人にめまいが起こった場合は、再発のサインの可能性があります。また、脳卒中が軽い場合はめまいが目立つだけで、他の症状はハッキリしないということもあるので注意しましょう。脳卒中とめまいは深い関係があるといわれています。再発の兆候や軽い脳卒中を見逃さないためにも病院で診てもらいましょう。
高齢者にめまいが続くと認知症になることも
高齢者の中にはめまいのために歩くのが怖くなり、外出の機会が減少し、家の中でもあまり動かなくなるなど活動量が低下してしまう人もいます。転ぶのを心配して歩かなくなると筋力が低下し、次第に寝ていることが増えてしまうでしょう。活動が減って刺激が少なくなると、高齢者の場合は認知症を発症する可能性もあります。脳卒中のように命にかかわるものではないとしても、めまいが続く場合は放置せずに受診しましょう。
しばらく休んでもめまいが続く場合
めまいが起きたときには体を休めることで、長くても数時間ほどでおさまるのがほとんどです。しかし、何度もめまいが起こる、数時間たってもめまいがおさまらないというときは受診をおすすめします。また、めまいは症状が軽い場合でも長期間にわたると日常生活の支障が大きくなるので、受診して原因を確認した方がよいでしょう。受診先としては「めまい外来」など、最近ではめまいの専門外来を開設している病院もあります。
めまいが続くときの検査
めまいの症状で受診すると、医師からどのようなめまいか(回転性か、浮動性かなど)、いつ頃から続いているか、また、めまいの頻度や持続時間などについて問診が行われます。さらに、めまい以外に気になる症状があるか、どのような状況で症状が現れやすいか、生活環境やこれまでの大きな病気なども確認します。
聴力検査
メニエール病などの耳の異常によるめまいは耳鳴りや難聴を伴うことが多く、聴力が低下することも少なくありません。聴力検査では、低い音~高い音までさまざまな周波数の音を使い、聞き取れるかを調べます。
足ふみ検査
脳幹や片方の内耳に障害がある人は、眼を閉じてその場で50歩、100歩と足ふみを続けると一方に回転してしまいます。足ふみ検査は、体のバランスを確認する検査の一つです。体のバランスを調べる検査には目隠しをしてまっすぐ歩けるか、目を開けているときと閉じたときに体のふらつきに違いがあるかなどを調べる検査もあります。
眼振(がんしん)の検査
めまいが続くときに眼(眼球)の動きを調べると、眼球が激しく揺れ動く眼振が現れていることが多いです。眼振はめまいがごく軽い状態でも比較的、現れやすいといわれています。そのため、眼振検査はめまいが続くときの検査としては極めて重要な検査です。検査では「フレンツェル眼鏡」という特殊な眼鏡を使い、眼振の有無や程度を確認します。
電気眼振図検査
フレンツェル眼鏡による検査は検査者が眼振を目で確認する検査ですが、電気眼振図検査は眼の周囲や額に電極をつけて眼の動きを電気的に測定します。
温度刺激検査
冷たい水やぬるま湯を耳に注入したときにめまいや眼振が起こるかを確認し、三半規管の働きの程度を調べる検査です。もし、三半規管に異常がなければ2~3分程度の軽いめまいや眼振が起こりますが、刺激を与えても反応が乏しい場合は三半規管の働きが低下している可能性があります。
神経学的検査
脳や手足などの神経に問題があると刺激に対する反応が遅れたり、しびれを感じたり、動きが悪くなることがあります。神経学的検査は反射をはじめ、感覚や運動などの機能を調べ、脳や神経に異常があるかを確認する検査です。
頭部のMRI検査
頭部のMRI(磁気共鳴画像装置)は脳の異常が考えられるときに行われる画像検査です。MRIは放射線を使わず、磁気によって脳梗塞や脳腫瘍などの有無や程度を調べます。
また、血圧の変動や糖尿病、貧血などが原因でめまいが起こることもあるので、血圧測定や血液検査なども行われます。
自分でできるめまいが続くときの対処法
めまいが続く場合に自分でできる対処法をみていきましょう。
めまいが起こりやすい状況を知る
めまいは、頭の向きによって起こる場合と起こらない場合があります。めまいが続くときは、頭の向きでめまいの程度がどのように変わるのかを知ることが大切です。めまいが起きた場面を振り返ってみるとよいでしょう。
めまいが和らぐ方向に頭を向ける
めまいが起こりやすい状況がわかったら、その状況を避ける、また、めまいが起きたときにはめまいが和らぐ方向に頭を向けるとよいでしょう。なお、良性発作性頭位めまいは慣れることで少なくなるといわれ、リハビリ治療としてめまいが起こる方向にあえて頭を向けることもあります。医師の指示に基づいて行いましょう。
めまいが続くときはしばらく安静に
回転性めまいが起きた場合、動くとめまいがひどくなる可能性があるので体を休ませることが大切です。倒れてケガをしないように座る、横になるなど落ち着いて安全にも気を配りましょう。車の運転や機械などの操作中は危険のないように運転や操作を止めてください。耳の異常で起こるめまいは、しばらく静かにしているとほとんどのめまいは落ち着きます。
タバコの吸い過ぎに注意!
タバコを吸い過ぎると血管が収縮して血流が悪くなります。脳や耳の血流が悪くなると酸素不足となって機能低下が起こりがちです。めまいが続くときはタバコを控えましょう。
めまいが続くことがないようにするには
めまいを防ぐにはどのような方法があるのでしょうか。
急な体の動きを控えましょう
めまいの程度を軽くし、めまいが起こる回数を少なくするには急な動きを少なくすることが大切です。起立性低血圧など血圧の大きな変動によってめまいが起こる人は、体を一気に起こさず、ゆっくり段階をつくって起き上がる癖をつけるとよいでしょう。湯船から出るときも血圧が変化しやすいので、急な動作を控えましょう。
同じ姿勢に注意!肩こりの予防を
スマホやパソコンなどで長時間、同じ姿勢をとっていると頸性めまいと呼ばれる首からくるめまいが起こることもあります。頸性めまいは首周囲の筋肉の緊張、また、首をねじったことによる血管や神経の圧迫などで起こるめまいです。同じ姿勢にならないように意識的に休憩をとったり、ストレッチをしたり、血行促進を心がけましょう。
ストレスや過労によるめまいを防ぐ
ストレスや過労によって自律神経の働きが悪くなると、フワフワした浮動性のめまいが続くこともあります。強いストレスや過重な負荷が続くとうつ状態になることも多く、うつ状態によるめまいが起きたり、寝不足がめまいの引き金になったりするので要注意です。対策としてはストレスや過労に気づき、無理をしないこと、また、食事や睡眠などの生活リズムを整えて自律神経の働きを高めるとよいでしょう。
視力に合った適切な眼鏡を使いましょう
一方の眼が白内障や緑内障などで視力が低下すると、左右の眼から入る情報に食い違いが生じて回転性のめまいが起こることがあります。視力が極端に低下して眼鏡やコンタクトレンズが合わなくなるとめまいが起こりやすいので注意してください。
内科的な病気がないかを病院で診てもらう
耳の異常によって起こるめまいの中には、高血圧や糖尿病などが影響していることもあります。めまいが続くときは内科や循環器内科、内分泌科などを受診し、内科的な病気がないかを確認するとよいでしょう。
また、高血圧で降圧剤を飲んでいる人は、降圧剤によって血圧が下がり過ぎてめまいが現れることもあります。適切な服用を心がけるとともに、めまがいが続くときには薬の服用について主治医に相談しましょう。
名医検索サイトクリンタル
名医検索サイトクリンタルでは日本全国の約30万人の医師から厳選された名医だけを掲載しております。手術数や外来の待ち時間など、受診する名医を決めるために必要な詳細情報を掲載しておりますので、受診先を検討される際の参考にしてください。
「どの名医に治療をお願いすればよいのかわからない!」とお悩みの方には、クリンタルの名医紹介サービスをお勧めしています。クリンタルが独自に厳選した「3,500人の有数の専門医」「35,000人の街の名医」の中から、あなたの病気/症状やご希望を考慮して、クリンタルの医師が最適な名医をご紹介します。