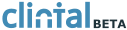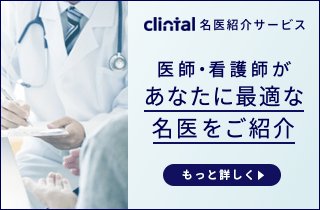アイスバケツチャレンジはALSという病気のためなんです!

ALS(筋萎縮性側索硬化症)の概要
ALSとは、英名Amyotrophic Lateral Sclerosisの略で、日本では筋萎縮性側索硬化症と呼びます。有名な元大リーガーの野球選手ルー・ゲーリックが罹った病期であることから、海外ではALSをルー・ゲーリック病と呼ぶこともあるようです。また最近ですと、バケツに入った氷水をかぶりALSの研究に寄付をするというアイスバケツチャレンジが社会現象化して、マイクロソフトのビルゲイツからiPS細胞の山中伸弥教授までが氷水をかぶりました。途中からその行為自体が注目されてしまいましたが、そもそもはALSの治療の研究のためだったんです。
日本では、2014年の時点で約9,200人のALS患者がいて、男女比は5:4でやや男性に多いようです。症状が見られる年齢で多いのは60~70歳代です。しかし、20~40歳代の働き盛りに発症する方も全体の6~7%います。
ALSは、2014年に放映された「僕のいた時間」というドラマで主人公が罹った病気です。ドラマを見た方は、この病気の進行の早さや治療の難しさ、そして生死に関わる難病であることがよく伝わったのではないでしょうか。ALSは発症すると時間とともに運動障害が進行する病気です。発症後2~5年で寝たきりとなり亡くなる方が多いようですが、進行が遅く10年以上生きられる方もいます。人工呼吸器によって延命する方法もあり、生命予後には個人差があります。
10年以上生きられる方もいるとはいえ、ALSの症状自体の進行は速いことが多く、経過とともに全身の様々な部位に症状が現れます。四肢麻痺や嚥下障害、コミュニケーション障害や呼吸筋麻痺などが主な症状です。どの症状も患者の生活の質に大きく関わるため、早期に発見して適切な治療をすることが大切です。
ALSの初期症状は、7~8割が手足、2~3割が会話や嚥下に異常が現れます。始めは軽い症状から始まり徐々に程度が重くなり、左右または他の部位に広がります。ALSの診断には、現れている症状のほか筋電図検査・神経伝達検査・血液検査によって総合的に行われます。よく似た病気と誤診したり、症状が進むまではっきりとした診断が付かず、診断が遅れるケースもあるようです。気になる症状があれば、早めに神経内科の専門医を受診しましょう。
下記は、ALSの初期に見られる主な症状と4つの病型です。
手足の症状
- 手足の筋肉がやせてきた
- 手足が突っ張る(こむら返りが起きやすくなる)
- 字が書きにくい
- 箸が使いにくくなった
- 筋肉疲労を感じる
- 手足の動きが制限される(思うように動かせない)
- 歩きにくい
- 手足が張れる・痛む
- 走れない・転びやすくなった
- 重い物を持てない
- 四肢の筋肉がピクつく
喉の症状
- しゃべりにくい
- 息苦しい
- 発音が不明瞭(パピプぺポ、ラリルレロがはっきり発音できない)
- 食事中むせやすくなった
- 食べ物が呑み込みにくい
- 舌が小刻みに波打つ
4つの病型
- 球麻痺型…喉や舌の筋肉の運動障害から始まるタイプで全体の約2~3割
- 上肢型…上腕・前腕・手の筋肉の運動障害から始まるタイプで全体の約4割
- 下肢型…大腿・下腿・足の筋肉の運動障害から始まるタイプで全体の約3割
- 呼吸筋麻痺型…呼吸に関係する筋肉の運動障害から始まるタイプでごく稀
ALS(筋萎縮性側索硬化症)の原因
ALSの原因は、現時点ではまだ解明されていません。神経の老化説やアミノ酸の代謝異常説などがあります。ただし、発症全体の5%を占める家族性のALSは、親や兄弟、祖父母の代にALS患者がいる場合に見られ、最近の研究では家族性ALS患者に特定の遺伝子が発見されています。
原因が解明されていないALSですが、発症するメカニズムは明らかにされています。ALSは、脳から脊髄に指令を伝える運動神経細胞(上位ニューロン)と脊髄の前角神経細胞から筋肉に情報を伝える神経細胞(下位ニューロン)の両方が障害されます。ALSでは、神経の伝達経路として機能している脊髄の神経細胞の側索という部分が、何らかの原因で変性(破壊・死滅)し、筋肉に情報が伝わらなくなり、運動が障害され徐々に筋肉が萎縮します。
ALS(筋萎縮性側索硬化症)の治療法
ALSの治療でリルゾール(商品名:リルテック)という薬が、進行を遅らせる効果があるとして1999年に日本で認可されています。しかし、リルゾールの効果に関しては、運動障害の進行を遅らせる効果が少なく、ある治験では延命効果が約2~3ヶ月であったという報告もあります。また、めまいや腹痛・下痢・肝機能障害などの副作用が起こりやすいこと、薬価が761円/錠と高いことなども、服用するメリットがあるかどうかを考える材料となります。
2015年に認可されたエダラボン(商品名:ラジカット)は、ALS進行抑制効果が高いことが治験で報告されています。副作用には腎機能障害や肝機能障害の可能性があるとされており、定期的な血液検査でのフォローが必要です。エダラボンの投与方法は、2週間毎日朝夕に分けて点滴を行い、その後2週間休み、再び2週間点滴を行うということを繰り返します。薬価はジェネリック(後発品)の場合、約2000~3000円前後で、薬価だけで換算すると一日約4000円かかることになります。
ALSの治療では、患者が運動障害を抱えながらもQOLを重視し――日常生活の質を維持し有意義に過ごせるように――症状を緩和する対症療法を行います。特にリハビリは、筋力低下に伴う運動制限による関節の拘縮を予防する目的で、発症早期から行うことが大切です。
対症療法の例
四肢麻痺の症状に対して
筋力低下の予防や筋力をアップさせるリハビリを実施します。筋力を補助するサポーターやテーピング・杖・車いすなどの装具を利用して運動をする訓練を行います。
嚥下障害に対して
むせないように呑み込むリハビリを行います。症状が進行した場合には、皮膚の外から胃に通る穴をあけてPEG(胃瘻)を作り液体栄養食を注入する方法も検討します。
また、嚥下障害が進むと唾液を呑み込む際に誤嚥して誤嚥性肺炎を起こすのを予防するため、唾液の分泌を抑える注射薬や軟膏の使用、外科手術や放射線照射などを行います。
構音障害(はっきり話せない)に対して
コミュニケーションは、QOLにとって非常に大切です。言語療法で話す訓練をするほかに、話すことに障害が生じてもコンピューターを通していろいろな人とコミュニケーションをとることができるよう、脳波や脳血流・まばたきや眼球の動きで操作できるコンピューターの使用訓練を取り入れます。
呼吸筋の障害に対して
呼吸するための筋肉の障害が進むと、人工呼吸器の導入を検討する。NIPPV(非侵襲的陽圧換気法)とIPPV(侵襲的陽圧換気法)があり、後者では気管切開や気管挿管の必要があります。人工呼吸器の使用は延命治療としてとらえられるため、患者の倫理観や意思を尊重して装着を決定します。
ALS(筋萎縮性側索硬化症)の最新治療
ALSでは、運動神経細胞が破壊され徐々に減ります。普通の神経細胞は再生できませんが、脳の一部にある「神経幹細胞」は、再生が可能です。この原理を利用し、脊髄に幹細胞由来運動ニューロン細胞を移植して機能を再生しようとする研究が数年前から続けられています。
また、2012年には、京都大学のiPS細胞の研究グループが、ALSの症状を抑える化合物を発見したという報告があります。あるALS患者の運動神経の中にTDP-43というタンパク質の変性を発見し、そこにアナカルジン酸という化合物を加えたところ、変性したTDP-43タンパク質が減少したということです。これは、ALSの進行を抑える治療薬の開発のヒントになるのではないかと期待されています。
名医検索サイトクリンタル
名医検索サイトクリンタルでは日本全国の約30万人の医師から厳選された名医だけを掲載しております。手術数や外来の待ち時間など、受診する名医を決めるために必要な詳細情報を掲載しておりますので、受診先を検討される際の参考にしてください。
「どの名医に治療をお願いすればよいのかわからない!」とお悩みの方には、クリンタルの名医紹介サービスをお勧めしています。クリンタルが独自に厳選した「3,500人の有数の専門医」「35,000人の街の名医」の中から、あなたの病気/症状やご希望を考慮して、クリンタルの医師が最適な名医をご紹介します。