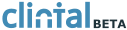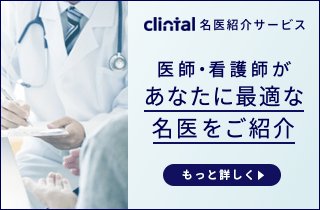症状・疾患別受診すべき医療機関-⑩緩和ケア

緩和ケアは大病院だけではなく、クリニックでも受けられます
がん患者が多い超高齢社会の日本で、最近脚光を浴びるようになってきた「緩和ケア」。
緩和ケアは大病院だけではなく、クリニックでも受けることができるのですが、今回は緩和ケアでクリニックがいいのか大きい一般病院がいいのか、という点に関してお話していきます。
緩和ケアは受けたいときに受けられない場合があります!
そもそも医学界では、「がん早期の頃から緩和ケアを大きな柱の一つにすべきである」という考え方が主流になりつつあるのですが、一般的には、まだ緩和ケア=「最期の時」「もうこれ以上何も治療できない」というイメージが根強いため、「緩和ケアの受診を決める」ということは患者さんにとって大きな意味を持つ場合があります。
しかし、いざ病院を受診し始めて「この病院で緩和ケアを受けたい」という心持ちでいても、「順番待ちです。入院まで半年間ほど待ちます。」と伝えられたら、いかがでしょうか。(詳しくは待機期間に関するこちらのコラムを参照してください)
特に、がんのために一刻を争うほどの激しい痛みが生じていた場合、そんなに待てないと思うこともあるでしょう。
ですから、まずは緩和ケアを受ける病院を決める前に、「待機期間はどれほどか」ということについて情報収集する必要性があります。前述したコラムでもご紹介した通り、ごく一部の病院ですが、待機期間をホームページに掲載している病院もありますし、実際にその病院を受診する前に、おおよその待機期間を問い合わせてみるのも良いでしょう。
では、次に緩和ケアを受けられる病院とクリニックの違いについてご説明します。
緩和ケアの病院とクリニックの違いは?
緩和ケアについては、ズバリ、病院でもクリニックでも診療内容にあまり変わりはありません。緩和ケアでは、疼痛緩和のためにモルヒネなどの麻薬を投与することがありますが、特に侵襲的な治療(手術など)をするわけではないからです。
ただし入院と通院では違いがあります。病院でも外来しかやっていないところもあれば、クリニックでも入院まで可能なところがありますが、入院と通院では様々な点で異なってきます。
例えば、使える薬や治療法です。入院であれば、強い痛みを抑えるために強めの鎮痛薬を使っても、呼吸が停止しないかどうか常にモニターされているので、安心して薬を使えますが、通院の場合には万が一のことを考えるといきなり強い薬を使うのは難しく、徐々に調整していくしかないです。
また入院の場合には、病院でもクリニックでも上で述べたような待機期間が発生することがあります。緩和ケアを受診される方の中には、入院が必要なレベルになるまで我慢する方も少なくないですが、待機期間を少しでも短くするためには、あらかじめ外来通院から始めておいた方がいいでしょう。なぜならば、すでに通院している状況であれば、入院が必要になった場合に適切なタイミングで受け入れてもらえるからです。
自分に合った病院・医師を探そう
緩和ケアで病院や医師を選ぶ際には、待機期間に加え、疼痛などの診療の質や精神的なケアも非常に重要な要素です。「包括的なケアの質」について病院やドクターの評価を調べ、ご自身に合った受診先、かかりつけの先生を探すようにしましょう。
名医検索サイトクリンタル
名医検索サイトクリンタルでは日本全国の約30万人の医師から厳選された名医だけを掲載しております。手術数や外来の待ち時間など、受診する名医を決めるために必要な詳細情報を掲載しておりますので、受診先を検討される際の参考にしてください。
「どの名医に治療をお願いすればよいのかわからない!」とお悩みの方には、クリンタルの名医紹介サービスをお勧めしています。クリンタルが独自に厳選した「3,500人の有数の専門医」「35,000人の街の名医」の中から、あなたの病気/症状やご希望を考慮して、クリンタルの医師が最適な名医をご紹介します。